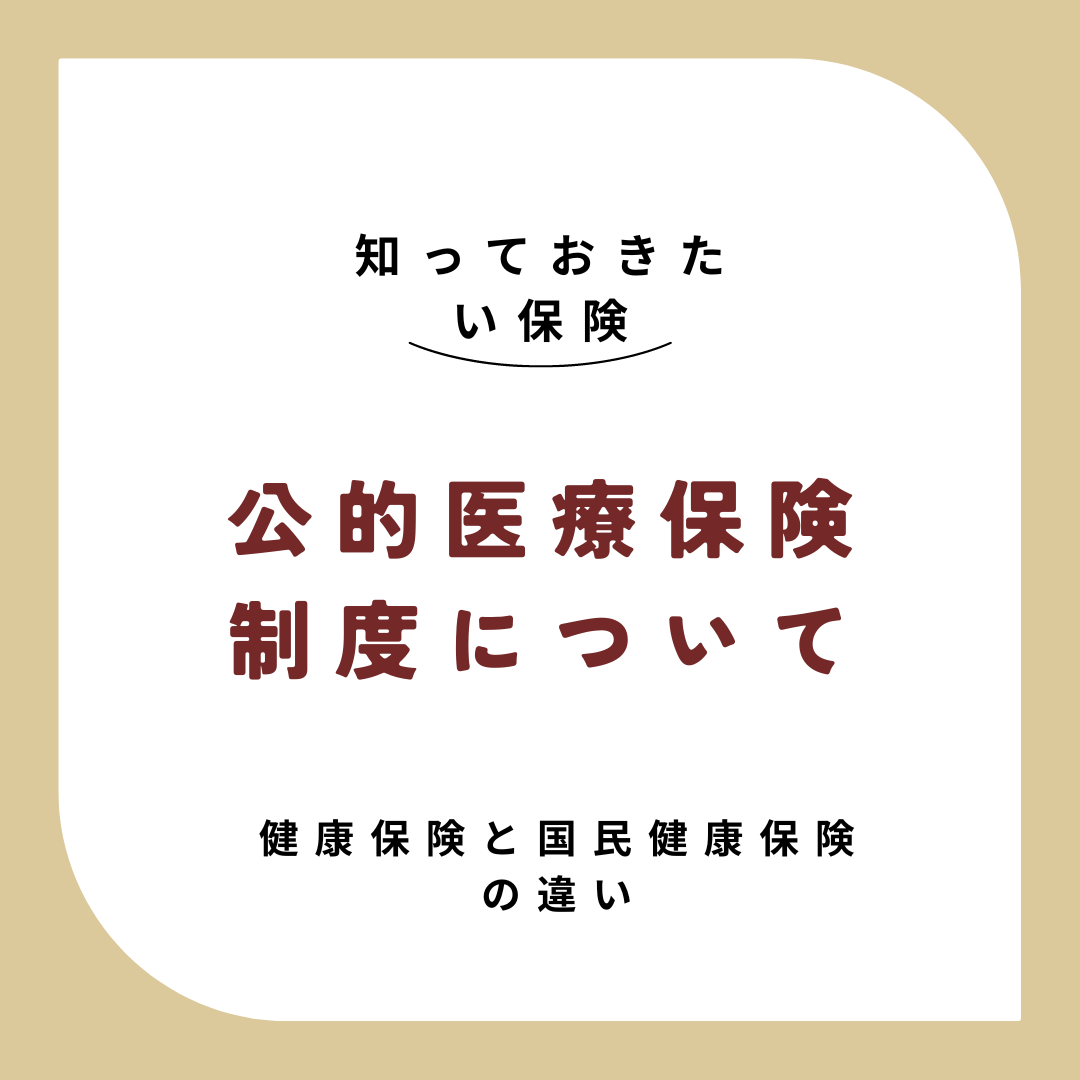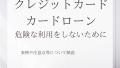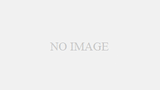日本は「国民皆保険制度」を採用しており、すべての国民が公的医療保険に加入することが義務づけられています。
公的医療保険制度は、国や地域によって異なる健康保険制度が存在し、それぞれの制度には異なる健康保険の違いがあります。
公的医療保険には、健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度の3種類があります。それぞれの制度の加入者は、働き方や年齢によって異なります。
この記事では、一般的な公的医療保険制度とその加入者の違いについて、FPの目線から詳しく解説します。
健康保険と国民健康保険の加入者の違いについて
健康保険と国民健康保険、名称はよく似ているので同じでしょ?と思うかもしれませんが、実はこの2つは大きな違いがあります。
健康保険と国民健康保険は同じ公的医療保険なのですが、この2つは別々に扱われます。
「健康保険」と「国民健康保険」では、何が違うのか?というと まず一番の違いは、加入者です。
簡単に言うと、「健康保険」には、会社で働く人(社長、役員及び従業員と、その被扶養者)が加入します。
これに対して「国民健康保険」の加入対象者は、個人事業主や自由業の方、学生、失業中の人など、健康保険(各種共済)に加入していない人達です。
最近増えてきたフリーランスの方のような個人の事業主は、1人社長みたいな立場ですが、医療保険制度の加入については、国民健康保険です。一方、法人の会社の社長は健康保険となります。
今のあなたの立場なら、どちらの健康保険に入るべきか?を知っておいてください。
健康保険と国民健康保険の保険者の違いについて
公的医療保険には、保険者(ほけんじゃ)といって、民間保険でいうところの保険会社にあたる組織が大きく3つあります。
まず、「健康保険」については、全国健康保険協会と健康保険組合の2つがあります。
- 「全国健康保険協会」・・・ここが行う保険を「全国健康保険協会管掌健康保険」(協会けんぽ)と言います。
- 「健康保険組合」・・・ここが行う保険を、「組合管掌健康保険」(組合健保)と言います。
一方、国民健康保険は、都道府県、市区町村、または国民健康保険組合の2つです。
自分がどの保険者の保険に加入しているか?を把握しておきましょう。
保険者の違いによって、受けられるサービス内容が違ってきますので、その場合、どこに申請すればいいのか?を知っておくことで、相談もしやすくなります。
健康保険と国民健康保険の給付の種類について
公的医療保険制度での給付とは、簡単に言うと、加入者に必要なお金を出すことです。これは保険者の義務です。

健康保険と国民健康保険の給付の種類はほぼ同じですが、次の3つの違いがあることは覚えておいてください。
1、国民健康保険は、業務上の病気やケガも対象となります。
2、国民健康保険は、所得補償の性質のある、傷病手当金や出産手当金が(任意給付だが)事実上ありません。
3.保険料(税)は、健康保険では報酬額により決まりますが、国民健康保険は、市区町村により異なります。
国民健康保険は、仕事をしているときの病気やケガも対象なので、万が一おこった場合は保険を使いましょう。
一方、健康保険は業務での給付は対象外ですが、そのかわり労災保険で給付される仕組みです。
まとめ
公的医療保険制度については、細かい決まりがたくさんあります。今日お話ししたのはほんの一部の内容ですが、まずは基本的なこととして覚えておくと、役に立つかと思います。
次のお話をも引き続き、公的医療保険制度|健康保険・国民健康保険の特徴や違いについて解説していきたいと思います!
参考
FP
最新記事 by FP (全て見る)
- 働きながら年金を受給できる?給与収入がある場合でも老齢年金を受け取ることができます - 2023年10月25日
- 公的医療保険制度|健康保険・国民健康保険の特徴や違いについてその1 - 2023年9月5日
- クレジットカードやカードローンはもしかして危険かも?利用する際の注意点 - 2023年8月30日