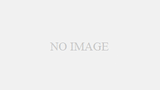ゲームは体にどんな悪影響があるのか?〜ゲーム依存とそのリスク〜
近年、私たちの生活においてゲームは大きな存在となっています。娯楽として楽しむ分には問題ありませんが、行き過ぎたゲームプレイが心身に悪影響を与えるケースが増えています。今回は「ゲーム依存」や「ゲーム障害」と呼ばれる問題について、最新の情報を交えてご紹介します。
ゲーム障害とは?
2019年、世界保健機関(WHO)は、ゲームのやりすぎによって日常生活に支障をきたす状態を「ゲーム障害(Gaming Disorder)」として、国際疾病分類(ICD-11)に正式に追加しました。これはアルコール依存や薬物依存と同じように、治療が必要な精神的健康の問題とされています。
ゲーム依存の主な特徴
- 10代の若者に多い
特に発達段階にある若年層は、ゲームからの刺激に強く反応しやすく、依存状態に陥るリスクが高いとされています。 - オンラインゲームが中心
依存に陥っている人の多くが、対人要素が強く、終わりが見えにくいオンラインゲームをプレイしている傾向があります。 - 生活習慣の乱れ
食事や睡眠、学校や仕事など、日常生活がゲーム優先となって乱れやすくなります。 - 暴力的なゲームによる影響
一部の研究では、暴力的なゲームを長時間プレイすることで、他者への共感力が低下し、攻撃性が高まる可能性があると報告されています。
治療とその課題
ゲーム依存に関する相談の約4割が「親だけが来ており、本人は治療に来ない」というケースです。そのため、早期の発見と本人の自覚が治療への第一歩となります。
現在、日本でも一部の病院や精神科で「ゲーム障害」の専門外来が設けられており、治療法の研究も進んでいます。WHOによる疾病分類への追加によって、今後は保険適用や社会的支援も進むと期待されています。
ゲームはすべて悪いのか?
もちろん、ゲームすべてが悪影響を及ぼすわけではありません。近年ではeスポーツの発展により、ゲームが新たなスポーツとして認知され、プロの世界で活躍する人もいます。大切なのは、「どれくらい」「どんな目的で」ゲームをするのかというバランスです。
ゲームとの適切な付き合い方を考え、健康的なライフスタイルを保つことが、現代を生きる私たちにとってますます重要になっています。家族や周囲と協力しながら、依存を防ぎ、ゲームの良さを活かせる環境を整えていきましょう。
学校や保護者が知っておきたい注意点と対応
ゲーム依存は本人の自覚が乏しいケースが多く、早期に周囲が気づいてサポートすることが非常に大切です。特に10代の若者は、家庭と学校が連携しながら支援することで、依存を未然に防ぐことができます。
学校関係者向けの注意点
- 授業中の集中力の低下に注目
眠そうな様子や注意散漫が続く場合、夜間のゲーム過多が疑われます。 - 友人関係の変化に注意
突然孤立する、あるいは特定の友人とだけ強く結びついている場合、オンラインゲーム上での人間関係が関与している可能性があります。 - 保護者との連携を重視
家庭での様子を共有することで、生活リズムの乱れなど早期に気づけます。 - ゲームを禁止するより「使い方の指導」
頭ごなしの禁止では反発を招きます。自己管理の力を育てる声かけが有効です。
保護者向けのチェックリスト
以下に当てはまる項目が多い場合、ゲーム依存の傾向があるかもしれません。
✅ ゲームの時間がどんどん長くなっている
✅ ゲームをやめさせようとすると激しく怒る
✅ 食事や風呂など日常生活が後回しになる
✅ 夜更かし・昼夜逆転が続いている
✅ 成績や学校生活に影響が出ている
✅ ゲーム以外の趣味や活動に興味を示さない
✅ ゲームを隠れてこっそりしている
✅ 家族との会話が減っている
✅ ゲーム機やスマホがないと落ち着かない
✅ ゲーム仲間とのチャット・通話を手放せない
対処法のポイント:
・まずは子どもを責めるのではなく、日常の会話から状況を探ることが大切です。
・ルール作りは一方的に押しつけず、「一緒に決める」ことが成功のカギです。
・困ったときは医療機関やスクールカウンセラーへの相談も検討しましょう。
最後に
ゲームは楽しみ方次第で、交流や学習、競技など多様な可能性を秘めています。しかし、その裏にある依存のリスクも、しっかりと向き合う必要があります。特に成長期の子どもたちにとっては、環境や支援次第で未来が大きく変わります。
家庭・学校・社会が一体となって、ゲームと健康的に付き合える環境を整えていきましょう。
※このコラムはベースで作成した文面をもとに生成AIを使用してまとめたものです。記事内容におかしな点(事実要素で違っていた場合は訂正いたします。考え要素は賛否で構いません)などがあれば
みなみやま かつのり
最新記事 by みなみやま かつのり (全て見る)
- ラジオカフェ「KYOTO SOCIAL WAVE」 - 2025年12月9日
- ゲーム依存について - 2025年10月20日
- iAnswer株式会社と特定非営利活動法人京都教育サポートセンターが業務提携契約を締結 - 2025年7月8日